建築・インテリアの現場では、「パース」という言葉ひとつで語られることが多くあります。
しかし実際には 広告用パース と 打ち合わせ用パース では、目的も表現も制作プロセスも全く異なります。
この違いを理解しないまま発注してしまうと、以下のようなすれ違いが生まれてしまいます。
- 施主との認識が合わず、打ち合わせが迷走する
- 広告段階なのに“地味に見える”パースで魅力が伝わらない
- 不必要に作り込みすぎて時間もコストも膨らむ
- 逆に、広告用なのに情報が足りず世界観が伝わらない
この記事では、パース制作のプロとして、
そしてインテリアコーディネーターとしての一次体験を交えながら、
「広告・PR用パース」と「打ち合わせ用パース」の本質的な違い を解説します。
工務店・インテリアデザイナーが外注を活用する際のポイントまで、
実務で役立つ視点でまとめました。
広告・PR用パースとは?目的と役割
広告・PR用パースの目的は、
「世界観を魅せる」
「ブランドの価値を高める」
という点にあります。
主に以下のような用途で活用されます。
- 竣工写真の代替ビジュアルモデルハウス・分譲住宅の広告
- チラシ・パンフレット・Webバナー
- SNS配信用ビジュアル
- プレゼン資料(初期のイメージ訴求)
広告用パースの特徴
- 光の演出が強い
自然光・陰影・反射をコントロールし、“魅せる”画づくりを行います。 - スタイリングの作り込み
家具・小物・アート・植物など、空間の世界観を最大化するための演出が入ります。 - Photoshopによる仕上げが前提
質感補正・色調整・ノイズ処理など、広告レベルの美しさまで作り込みます。 - 実際の仕様より少し魅力的に見せることがある
広告目的では、写真以上の見栄えを求められることもあります。
軽井沢の一棟貸し「YURAGI」プロジェクトでは、インテリアデザインを手掛けた荒井詩万さんの世界観をどう表現するかが重要でした。打ち合わせ用とは異なり、「雰囲気・空気感・光の表現」 を優先し、ブランド価値が伝わる広告クオリティが求められました。

打ち合わせ用パースとは?現場が求める「正確性」

打ち合わせ用パースは、広告用とは目的がまったく異なります。
こちらの目的は 「意思決定を早めること」 です。施主・設計者・ICの認識を揃え、手戻りを防ぐために使われます。
打ち合わせ用パースの特徴
- 図面通りの正確性が最優先
寸法・高さ・窓位置・造作家具など、細部のズレが工事トラブルにつながるため、誤差のない再現性が求められます。 - スタイリングは最小限
素材・色・配置を判断するための“情報提示”が中心で、装飾は控えめにします。 - 変更前提なのでスピードが重要
広告並みに作り込む必要はなく、“判断できる状態”を優先します。 - 色・素材の見え方を揃えるために使う
照度や陰影で見え方が変わるため、ICとしてはここが最も大切なポイント。
インテリアコーディネーターの立場で最も重視しているのは、色や素材の“見え方をどれだけ正確に伝えられるか” という点です。ただし、これはパース制作に限らず、実物を写した写真であっても同じ課題を抱えています。
写真は「撮影時間・自然光の入り方・カメラ設定・室内照明の色温度」など、さまざまな条件によって色が大きく変化します。肉眼で見たままをそのまま一枚の画像で完全に再現することは、実はとても難しいことなのです。
ましてパースは“作りもののビジュアル”です。実写以上に、光の条件やモニター環境による差が出やすく、どれだけ精度を高めても「完全再現」は不可能に近いというのが現実です。
だからこそURAKATAstudioでは、パースはあくまで“イメージ共有のためのツール” として活用しつつ、最終判断は必ず実際のサンプル(現物材・クロス帳・タイル・床材など)で確認していただくことを強く推奨しています。
パースで“雰囲気”と“方向性”を共有し、実物サンプルで“確かな質感と色味”を決める。
この二段構えこそが、失敗しない空間づくりにおいて最も確実でプロフェッショナルな進め方だと考えています。
工務店・インテリアデザイナー間で起こる“すれ違い”の正体
広告用パースと打ち合わせ用パースを区別せずに発注すると、現場では次のようなすれ違いが起きます。

工務店でありがちなケース
- 図面が確定していないのに広告レベルを求めてしまい高額になる
- 変更が多い段階なのに作り込みすぎて時間がかかる
- 簡易パースを提出したら地味すぎて魅力が伝わらない
根本にあるのは、「どの段階で、どのパースが必要か」 が明確でないことが考えられます。
インテリアデザイナーが感じる課題
- デザイン意図を言葉だけで伝えるのが難しい
- プレゼンでは広告用の“魅せるパース”が必須だが自分で作成するのが困難
- 仕様確定では正確な“打ち合わせパース”が必要
- 1枚で両方を満たそうとすると中途半端になる
ICは世界観と正確性の両方を扱うため、パースの使い分けが提案の質を左右します。
外注でうまく進めるためのポイント
広告用と打ち合わせ用の違いを理解した上で外注すると、制作プロセスが驚くほどスムーズに進みます。
- まず「目的」を明確に伝える
・広告・PR用?
・打ち合わせ用?
・SNS用?
・初期提案用?
これだけで必要な仕上がりレベル、価格、制作ボリュームも変わります。 - 図面・仕様の共有は丁寧に
・平面図・立面図・展開図
・色品番・素材
・造作家具の寸法
・参考写真
パース制作の現場で特に誤解されやすいのが、「高さ」と「デザイン」の情報共有 です。よく、平面図だけでパース制作者はすべてを理解して作成することが可能、とばかりにパースを依頼されるケースがありますが、平面図には“高さ情報”が載っていないことが多く、この状態では 正確な立体の再現はほぼ不可能 です。
たとえば「窓」を例に挙げます。
平面図からは 窓の“横幅” は分かりますが、次の情報は読み取れない場合が多いのです。
- 床から窓の取り付け位置までの高さ
- 窓本体の高さ
- 窓のデザイン(格子の有無・カラーなど)
- 枠の太さ
- ガラスの仕様
たとえ「幅・取り付け高さ・窓高」が分かったとしても、デザインそのものが分からなければ正確に立体を起こすことはできません。もちろん、掃き出し窓なら「床から約2000程度の窓」など、一般的なセオリーから推測することはできます。
ですが、クライアントが正確な再現を求めている場合、“推測”に頼ったままでは正しいパースは作れません。
だからこそ、高さ情報(立面・展開・断面図)と、窓・建具のデザイン情報を必ず共有することが重要です。
パースは「平面を立体化するだけの作業」ではなく、「実際の空間をなるべく正しく視覚化する作業」 です。そのためには、平面図だけでは不十分で、高さ・仕様・デザインといった追加情報が欠かせません。必要な情報が揃っていれば、パースの精度は一気に上がり、打ち合わせのすれ違いや手戻りも大きく減らすことができます。
パースを使い分けることで得られる具体的な効果
広告用と打ち合わせ用を正しく使い分けると、以下のような効果が得られます。
工務店・設計事務所の場合
- 施主との意思疎通が早い
- 手戻りが減り、現場がスムーズ
- 提案時の魅せ方が統一されてブランド力が上がる
インテリアデザイナーの場合
- 世界観が正確に伝わる
- 色・素材の認識のズレを防げる
- プレゼン → 仕様確定までの導線がスムーズ
- 意思決定が早くなる
まとめ
- 広告・PR用パースは“魅せる”ためのビジュアル
- 打ち合わせ用パースは“正確な判断”を促す資料
- 両者の役割はまったく異なる
- 目的に応じてパースを使い分けることで、提案力も効率もアップ
- 外注活用は工務店・ICの業務を大幅に軽減し、成約率向上にもつながる
パースは「ただの絵」ではなく、意思決定と提案のためのプロフェッショナルツール です。
初期コストを抑えつつ最適なパース提案を。
提案の初期段階では、これからデザインが変わることが前提です。そのため、いきなり広告レベルの作り込みをする必要はありません。むしろ “最小限の作り込みで、魅力だけはしっかり伝えるパース” が最も効果的です。

ファーストプレゼンでは、
- 価格を抑えつつ
- 方向性を共有し
- お客様の心に印象を残す
この3つが重要なポイントになります。
URAKATAstudioでは、そうした実務ニーズに合わせて、初期提案には 価格を抑えた簡易パース を採用し、その後の変更に柔軟に対応できる プロジェクト追随型プラン や、修正ごとに費用が積み上がる負担を避けたい方向けの 月額サブスク型プラン など、進行方法やプロジェクト規模をヒアリングし最適な進め方をご提案いたします。
最初から高額な仕上がりを求めるのではなく、「初期はシンプルに、進行に合わせて必要な部分だけ段階的に整えていく」─これが、コストとスピードとクオリティのバランスを取る最も合理的なパース活用法です。
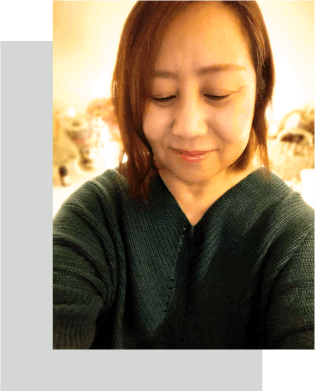
兵庫県神戸市・明石市を拠点に、全国の建築・インテリア関連企業様にオンラインでサービスを提供しております。近隣エリアのお客様には、対面でのきめ細かな打ち合わせも承っています。
建築パースに関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
24時間以内に回答いたします。










